風邪症候群
風邪症候群とは、ウイルスや細菌などの病原体によって引き起こされる、上気道(鼻や喉)の炎症による一連の症状のことです。風邪は多くの人がかかる一般的な病気で、通常は自然に治癒しますが、時には重篤な合併症を引き起こすこともあります。

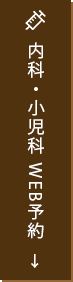
Medical

咳、発熱、頭痛、インフルエンザ、肺炎、糖尿病、生活習慣関連(高血圧、高脂血症、肥満等)、貧血、喘息、肺気腫、不整脈、動脈硬化など内科一般の診察を行います。
風邪症候群とは、ウイルスや細菌などの病原体によって引き起こされる、上気道(鼻や喉)の炎症による一連の症状のことです。風邪は多くの人がかかる一般的な病気で、通常は自然に治癒しますが、時には重篤な合併症を引き起こすこともあります。
血圧が高い状態が続く事で血管の壁に圧力が掛り、その結果、血管を傷めて次第に血管が硬くなり動脈硬化へとつながります。
高血圧の原因は特定されていませんが、遺伝的要因と食生活(塩分の高い食事)や嗜好(喫煙・飲酒)過多、または運動不足や精神的なストレスなどの環境的要因が重なって引き起こされると考えられています。
脂質異常症とは、血液中のコレステロールや中性脂肪などの脂質の値が正常範囲を超えたり、低下したりする状態をいいます。自覚症状がほとんどありませんが、放っておくと動脈硬化を進め、心筋梗塞や脳卒中などの重大な合併症を引き起こす可能性があります。脂質異常症は「サイレントキラー」とも呼ばれるほど、油断できない病気です。
糖尿病とは、血液中のブドウ糖(血糖)の値が高くなる病気です。ブドウ糖は、食べ物から摂取した炭水化物が消化吸収されて作られるエネルギー源で、インスリンというホルモンの働きによって、体の細胞に取り込まれます。すい臓が分泌するホルモンで、不足したり、効きにくくなったりすると、ブドウ糖は体の細胞に取り込まれずに血液中に残ってしまいます。これが血糖値の上昇につながります。
加齢や薬の副作用などによって骨密度が低下する病気です。
女性ホルモンの低下と関わりが深いため、40代以降の女性には早めの骨密度検査をお勧めします。
当院では日本骨代謝学会、日本骨粗鬆症学会が作成する原発性骨粗鬆症の診断基準(2012年改訂版)に準拠した『日立ALPHYSA(X線骨密度測定装置)』を導入しています。DXA法による前腕の骨密度を測定しており、より精度が高く、数分で終わる患者様への負担の少ない検査です。
骨粗鬆症になると、転ぶ、尻もちをつく等ちょっとしたはずみで骨折しやすくなります。背骨を圧迫骨折してしまうと背中や腰が丸くなったり、身長が縮んでしまったりします。また、高齢の方が大腿骨を骨折してしまうと回復まで時間がかかり、寝たきりの状態となってしまう可能性もあります。
骨粗鬆症は治療の出来る病気です。骨密度の低下を抑え、骨折を防ぐことにあります。まずはご自身の骨密度を把握し、食生活や運動習慣を改善し、飲み薬、注射など適切な治療へ繋げていきましょう。
リウマチとは、関節や筋肉、皮膚などに炎症を起こす病気です。代表的なものに「関節リウマチ」と「膠原病」があります。関節リウマチは、手足の小さな関節に炎症が起こり、関節が腫れたり痛んだりする病気です。膠原病は、全身の結合組織に炎症が起こり、関節だけでなく内臓や血管などにも障害を起こす病気です。膠原病には、全身性エリテマトーデス(SLE)やシェーグレン症候群などがあります。
逆流性食道炎とは、胃の内容物(胃液や消化されていない食べ物など)が食道に逆流して、食道の粘膜に炎症を起こす病気で、胃食道逆流症(GERD)とも呼ばれます。成人の約10〜20%が罹患していると推定されています。
高尿酸血症とは、血液中の尿酸の濃度が正常値よりも高くなっている状態です。尿酸は、細胞の代謝産物であるプリン体が分解されてできる物質で、通常は尿として排泄されます。しかし、プリン体の摂取量が多かったり、尿酸の生成量が増えたり、尿酸の排泄量が減ったりすると、血液中に尿酸が溜まってしまいます。これが高尿酸血症の原因です。
心房細動とは、心臓の上部にある心房という部分が不規則に高速で動く不整脈の一種です。心房細動になると、心臓のポンプ機能が低下し、血液の流れが悪くなります。その結果、動悸や息切れ、めまい、疲労感などの症状が現れることがあります。また、心房内に血栓ができて脳や他の臓器に詰まると、脳梗塞や心筋梗塞などの重大な合併症を引き起こす可能性があります。